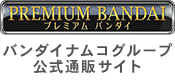仮面ライダーの生誕50周年を記念して製作された、『仮面ライダーBLACK SUN』でメガホンを取った白石和彌監督。これまでの作品は生々しくハードな人間ドラマを描いたものが多いですが、そこに人間らしさを感じさせ、魅力的に映します。そんな白石監督が撮った仮面ライダーとは。従来の仮面ライダーシリーズと一線を画す社会派のストーリーに、ヒーローの認識が揺れるかもしれません。

この度リリースする『HENSHIN by KAMEN RIDER』の『仮面ライダーBLACK SUN』コレクションで、メインデザインとなる「∞」を手書きで描いてくださった白石監督に、作品を手掛ける際に込めている思いから、『仮面ライダーBLACK SUN』の制作についてまでをインタビュー。ぜひ、こちらをお読みになってから、『仮面ライダーBLACK SUN』をご覧ください。
“変身!”というキャッチフレーズで知られる、仮面ライダー作品。その場のなりゆきや外的要因により戦う宿命を背負わされる主人公たち。彼らが不安や葛藤、挫折を味わいながら、次第に自分の中で覚悟を固めていく内面の変化こそ、仮面ライダー作品が持つ"タイムレスな価値"と捉え、服に袖を通す日常の過程で少しずつ自分をアップデートできる服を目指し、ファッションという切り口で「仮面ライダー」を再解釈・デザインするファッションブランド。
“普段の自分だったら逃げてしまうことを登場人物に真正面から向き合わせます。”
―まず、白石監督と仮面ライダーの出会いを教えてください。
『仮面ライダーV3』の再放送を小学生の頃に観ていました。怪人を特集している厚い本も読んでいましたよ。仮面ライダーより、怪人の怖い造形に惹かれていたみたいです。
―『仮面ライダーBLACK』は、当時観ていましたか?
中学生になっていたので、リアルタイムでは観ていなくて。ですので、『仮面ライダーBLACK SUN』のお話をいただいてから、改めて観直しました。大人になって観たからこそ理解できた部分も多かったです。特撮作品としてのツボを押さえていて、仮面ライダーとして外しちゃいけない部分も多々あって、改めて『仮面ライダーBLACK SUN』は難しいプロジェクトだと思いました。
―『仮面ライダーBLACK』は、どんなところが印象に残りましたか?
やっぱり怪人が印象に残っています。クジラ怪人は、最初は敵だったのに、いつの間にかBLACKと友情が芽生えて味方になる。あと、剣聖ビルゲニアは重要な悪役だと思っていたのに、途中からライバルじゃなくなっていくのが寂しかった(笑)。カニ怪人は強くて、あと一歩でBLACKに勝てそうだったのに……。そういった怪人が良かったので、『仮面ライダーBLACK SUN』でも登場させています。
―怪人に惹かれていた子どものころ、ヒーローになりたいという願望はありましたか?
ありましたよ。でも、ヒーローというより、違う自分になりたいという感覚。それは今でも持っています。なぜこの仕事をしているかというと、現実世界で自己実現できないことを叶えたり、自分の立場では発信できないメッセージを登場人物に代弁してもらったりできるから。理想の自分、言わばヒーローになれるんです。
―登場人物の感情を描くことや、作品の世界観を構築していくのは監督の魅力ですね。
そうですね。あと、制作過程でキャラクターを形成していく中で、ふと「こいつは俺だな」と思うこともあるんです。「それだったら、こういうことを言わせてみよう」と、普段の自分だったら逃げてしまうことを登場人物に真正面から向き合わせます。本当はこういうふうに生きたいと思う人生を作品中のキャラクターで描いて、現実の自分が反省することもあるんです。

―では、現実世界で、なりたい自分になるために必要なことは?
自分なりの考え方や生き方がしっかりあって、己を持つこと、ですかね。僕はできていないから、そうなりたいと思っています。
―脚本を書く際、自分と向き合う時間が多いのではないでしょうか?
多いです。表現は記憶や体験から生まれてくるので、普段から自分と向き合うのが大事。脚本を書く際はそれを意識しています。
“心が動くのは、何かが生まれる瞬間。”
―白石監督にとって、ヒーローとはどういう存在ですか?
孤独な自分と向き合って、ベターを選択していく。石ノ森章太郎先生が描く仮面ライダーは、涙の流れた線が印象的でした。常に悲しみを抱えているところが、色気を生んでいるんだと思います。そういう悲しみや、大きな宿命を背負って立ち向かうのがヒーローです。そこには善と悪がないから、ダークヒーローという存在が成立するんだと思います。
―カメラに映らない部分はどのように表現しようと考えていますか? 白石監督の作品は、肌に寄ったり血を映したり、寄れば寄るほど映っていない部分が映し出されているように感じています。
ずっと葛藤していますよ。こっちを映したなら、あっちのリアクションも必要と、すべてを映そうとすると尺が足りなくなってしまうので、なにを掬い取るか。切り取るより、切り捨てる部分のほうが圧倒的に多いので、恐怖を感じることもあるんです。俳優さんが素晴らしい演技をして、スタッフもこんなシーンになるとは思わなかったと感動することがあります。その瞬間は嬉しいけど、ちゃんと切り取って、観る人に届けられるのかと不安になる。すごい演技でも切り取れる部分はごく一部で、映せないものを何で置き換えられるか考えています。

―映画にはどんな力があるとお考えですか?
映画との出会いは、素晴らしい先生一人と出会うに匹敵する影響力があると思っています。それで人生が変わる人がいるし、生き方を見直すことも多い。遠い場所での営みを身近に感じられて、いろんなことを発見できる学校でもあります。文化や宗教が違っていても、僕らと同じように恋をして、挫折して、希望を持って、平和に暮らしたいと思っていると知れるのは、映画が持つ力のひとつだと思います。
―そんな白石監督が仕事をするうえで大切にしていることを教えてください。
映画監督として、次も作らせてもらえるとは思っていません。その1本でやりたいことを全部やって、次に繋がらなかったら辞めようと、最初に映画を撮った時から考えています。その気持ちを失わないように、クランクインする前に思い返すようにしています。
―すべての力を注ぐということですね。全力で撮影していると、どんな瞬間に心が動きますか?
いっぱいありすぎて、困っちゃいます。俳優さんが役を掘り下げて、想定以上になった時とか。今回も西島(秀俊)さんが変身するシーンは心が動きましたよ。変身シーンは数秒で終わっちゃうけど、最初の撮影時間は午前中いっぱい掛かったんですよ。それくらい集中して、変身シーンに賭けてきているのが伝わって感動しました。
―それは必見ですね!
映画監督をやっていると苦しいことが多いですが、俳優さんやスタッフから感動のプレゼントをもらえるんです。怪人のデザインひとつとっても、1年近く、ああでもないない、こうでもないと話し合って、いざ作り始めると思い通りにいかずに苦労して。いざ完成して現場に立ってもらうと、みんなで感動しました。そういった意味で心が動くのは、何かが生まれる瞬間かもしれません。演技や造形で、僕のイメージ以上のものを具現化してくれると心が動きます。『HENSHIN』のアイテムも感動しましたよ。作品にインスパイアを受けたデザインになっていて。そのキャップは、裏地に怪人の総柄を使うのはもったいないくらいカッコいい。Tシャツも着倒したいけど、貧乏性だから着るのに躊躇しちゃいます(笑)。

―ありがとうございます。Tシャツは厚手の生地を使っているのでへたらず、長く着ていただけると思います。このブーツは作中で50年前と現代を行き来することから着想を得て、1970年代に流行っていたサイドゴアブーツを採用しました。つま先の装飾のメダリオンは、親一人、子二人の大小ドットになっていて、創世王と仮面ライダーBLACK SUN&仮面ライダーSHADOWMOONの関係を表現しています。インソールには白石監督に描いていただいた「∞」のマークを入れています。この「∞」デザインはTシャツとCAPにも採用させていただきました。
時代を顧みつつ、デザインに意味を込めてストーリーを作っているのがいいですね。特撮を撮ってみて、ベルトやグローブなど、スタッフが道具ひとつひとつにストーリーを紡いで魂を宿らせていると改めて実感しました。モノの良さ、造形物のおもしろさを再認識しています。
“誰かにとっては助けになるけど、誰かにとっては迷惑になる。”
―『仮面ライダーBLACK SUN』は、白石監督にとって初めての特撮作品。これまでの作品と違いを感じましたか?
いいところをたくさん発見しました。基本的に特撮はメッセージを込めやすいんですよ。環境問題だったり核問題だったりを、あえてテーマに設定している作品が多いじゃないですか。そういう難しいことをてらうことなく入れやすいのは、特撮のいいところ。あと、特撮と対極にあるリアリズムの作品をいつも撮っているので、それと離れたところで造形しなければいけないのは、苦労したけど、すごくおもしろかった。たくさん学ぶことが多かったので、チャンスがあればまたやりたいです。普段の僕の作品には参加しない特殊造形のスタッフとか、特撮作品を作り続けている人たちと一緒に製作できたのもよかった。そういう人たちと話す時間が刺激的でした。
―スーツを着た演技は、白石監督のこれまでの作品にはないですもんね。
スーツは視界がすごく狭いことが分かりました。特撮では当たり前のことが、僕にとって当たり前じゃなかった。それを知った上で演出しないと大きな事故に繋がってしまうから、あまり無茶な演出はできないと、僕自身探り探りでした。普段から仮面ライダーを撮っているスタッフは、今放送している作品を撮っているから、こっちの現場に来られなくて。田口さん(特撮監督)にリードしてもらいました。
―仮面ライダーシリーズにおいて、“変身”は大きなキーワードですが、『仮面ライダーBLACK SUN』ではどのように捉えましたか?
そもそも“変身”ってすごい発明ですよね。相手にもはっきり、“変身”って宣言しますし(笑)。でも、それが実は重要だなとも思って。今回、田口さんに、「“変身”って言うんですか?」って聞かれたんですよ。僕としては、「え? 言わないの?」って(笑)。最近の仮面ライダーはあまり言わないし、僕が監督なら、なお言わなくてもいいんじゃないか、と。だけど絶対言いたかった。

―白石監督なりの仮面ライダーとしての表現が“変身”だったんですね。
そうなんです。「現実だったら、“変身”って言わないんじゃないか」って演出の方々にも言われましたけど、頑なに台本にいれました。
ー『仮面ライダーBLACK SUN』は、人間と怪人の共存という、SFでありながら現実に置き換えて考えられるテーマがあります。演出するにあたって、気をつけた部分はありますか?
SFと現実をどのように融合するかを踏まえたので、少しでも違うと思ったら何度も修正していって。もう少し特撮っぽい演出が多くてもいいのかなと思いましたが、極力リアルに寄せて作ろうと決めました。みんなが住みやすい世の中にしたいと考えていて、それが誰かにとっては助けになるけど、誰かにとっては迷惑になる。どちらが善か悪か、決められません。
―人間と怪人のような衝突は永遠に続くかもしれませんが、その点はどのようにお考えですか?
正義と別の正義の争いは、人類が現在までずっと繰り返していること。個人的にどこかで途切れて欲しいと思っていますけど、人間は愚かなので止める術を知りません。100年前のこともよく分かっていませんからね。でも、記録として映像を残せば、何か変わるのではないかと期待している部分はあります。歴史から学び、間違っていれば直して、次に託そうと努力することが大事。映画からたくさんのことを学んだ一人として、少しでも多くのことを映像に落とし込んで伝えていきたいです。
―『仮面ライダーBLACK SUN』は、仮面ライダーの生誕50周年を記念した作品です。その点も気合が入ったのではないでしょうか。
僕が初代を観直したように、生誕100周年を迎えた時に観直されると勝手に想定ながら作っていました(笑)。並々ならぬ気合いを入れようとスタッフたちで申し合わせ、スクリーンで観られるスペックで撮りました。
―楽しみにしている人が多いと思います。
この前、映画館に行ったら、「『仮面ライダーBLACK SUN』を楽しみにしています」と声を掛けられました。他の作品で言われたことないのに(笑)。それだけのビッグタイトルということですよね。多くの人に影響を与えているということを痛感したので、背筋が伸びる思いでした。『仮面ライダーBLACK』のリブート作品ですが、ベースになっている『仮面ライダーBLACK』のファンに喜んでもらえる要素を少しでも入れようと、似たシチュエーションやファンなら気づくシーンを組み込んでいるので、そこも楽しみにしてもらいたいです。
1974年生まれ、北海道出身。1995年に中村幻児監督が主宰する『映像塾』に参加。以後、若松孝二監督に師事。2010年に『ロストパラダイス・イン・トーキョー』で長編監督デビュー。2013年『凶悪』で新藤兼人賞金賞や第38回報知映画賞監督賞など、数多くの映画賞に輝き脚光を浴びる。2018年『孤狼の血』で第42回日本アカデミー賞優秀監督賞などを受賞。そのほか主な監督作品に、『日本で一番悪い奴ら』、『牝猫たち』、『彼女がその名を知らない鳥たち』、『サニー/32』、『止められるか、俺たちを』、『麻雀放浪記2020』、『凪待ち』、『ひとよ』など。

文・取材: 小松 翔伍